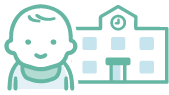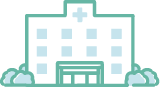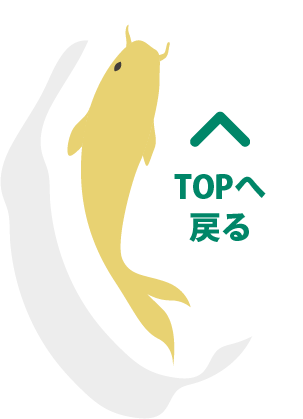本文
片貝の木遣りと古式玉送り(かたかいのきやりとこしきたまおくり)
印刷ページ表示
更新日:2010年7月12日更新
片貝の木遣りには、前唄(まえうた)・道中(どうちゅう)木遣り・奉納(ほうのう)木遣りの三曲があります。いずれも浅原神社秋季大祭(片貝まつり)の中核をなす花火の玉送り行事に欠かせない木遣り唄(うた)となっています。
古式玉送りは、明治初期に町内の花火をまとめて奉納、打ち揚げるようになってから始まったとされます。奉納大煙火と大書した玉箱に花火玉を入れ、幣束(へいそく)を立て注連縄(しめなわ)を張り、その前に御神酒(おみき)の酒樽(さかだる)三個を積み上げ、最後部には囃子(はやし)用の大小太鼓を載せた車を山車(屋台)とし、揃(そろ)いの印半纏(しるしはんてん)を着用、町内を門付(かどづ)けしてまわり神社に花火を奉納します。
木遣りは本来、その名のとおり大きな材木などを運ぶ時、力を合わせる為の掛け声から始まったもので、歌詞が少なく、囃子が多いほど古いといわれています。
浅原神社の秋季大祭は別名花火祭りともいわれ、江戸火消しの装束(しょうぞく)を模した組の半纏を着用、木遣りを唄いながらの玉送りは特異な祭り文化として近隣の村々に多大な影響を及ぼしました。毎年9月8日から10日にかけて開催されます。
文化財指定日 2001年7月23日


<関連リンク>